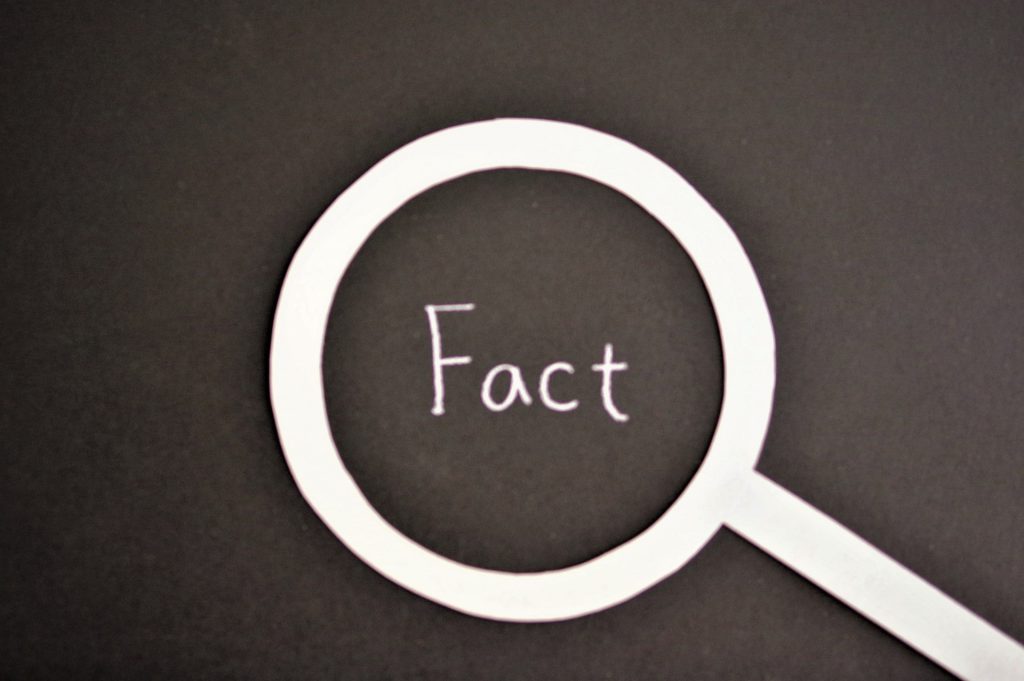持分なし医療法人M&Aと持分あり医療法人M&Aはどっちがお得?

INDEX
こんにちは。医院継承・クリニックM&A支援のメディカルプラスです。先生方から「持分あり」と「持分なし」、どちらが良いのかといったご相談をいただく機会が多くございます。平成19年の医療法改正により誕生した「持分なし医療法人」は、設立から17年を経て、いまようやく世代交代の時期を迎えつつあります。一方で、現在の医療法人M&A成約件数の多くは、いまだ「持分あり医療法人」によるものが中心です。弊社で医療法人の継承支援を行う際にも、「出資持分」や「財産権」といった言葉が頻繁に登場します。
医療法人には「持分あり」と「持分なし」という二つの形があり、どちらを選ぶかによって相続・贈与・M&Aの際の取り扱いが大きく異なります。一方で、初めて医療法人の継承に関心を持たれた先生にとっては、「持分」という言葉は耳にしたことはあっても、実際の意味や影響をイメージしづらい部分かもしれません。そこで過去の記事では、なぜ「持分なし医療法人」が生まれたのか、その制度改正の背景を解説しました。本稿ではそこから一歩進み、「持分あり」と「持分なし」それぞれの医療法人が、M&Aや医院継承の場面でどのように違いが出るのかを整理します。譲渡のしやすさ、創業者利益の扱い、そして相続税の観点など、医療法人をめぐる判断は将来設計に直結しますので、ぜひご自身のクリニックの未来を考える際の参考にしていただければ幸いです。
持分なし医療法人のM&Aが少ない理由
持分なし医療法人のM&A成約事例が少ないのには、大きく分けて二つの理由があります。「売りに出される法人がまだ少ないこと」と「持分あり法人からの移行が進んでいないこと」の二点です。
理由➀:売りに出される法人がまだ少ない
まず一つ目の理由は、持分なし医療法人が売りに出されることが少ない(持分なし医療法人がまだ売却の時期を迎えていない)という点です。この「持分なし医療法人」は、平成19年(2007年)の法改正で新たに生まれた制度です。それから17年経過しておりますが、開業時の医師の平均年齢がおよそ40歳ですので、医療法改正後の持分なし医療法人としてスタートした院長は57歳前後ということになります。院長先生がまだ第一線で診療を続けておられる年齢層であり、医院継承を検討するピークには至っていないケースが多いものと思われます。あと5~10年後ほど経過すれば、持分なし医療法人を設立した院長が60代後半になりますので、増加に転じると予想されます。ここからがようやく世代交代、という現実的なタイミングを迎えるとのではないでしょうか。
理由➁:「持分あり医療法人」からの移行が進んでいない
二つ目の理由として、旧法の持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行が進んでいないことが挙げられます。というのも、持分あり医療法人においては「財産権」が認められていることから、医師からの人気が根強いのです。国では持分なし医療法人への移行を推進していますが、権利を手放すことに対する心理的な抵抗は生じやすいと考えますので、順調に進捗しているとは評価しづらい部分があります。
厚生労働省の「種類別医療法人数の年次推移(令和7年)」によると、医療法人社団は全国で59,043件あり、そのうち持分あり医療法人が35,766件(約61%)、持分なし医療法人が23,268件(約39%)を占めています。平成19年の医療法改正以降17年間で、持分なし医療法人は約2万3,000件増加した一方、持分あり法人の減少はおよそ6,600件にとどまっています。このことからも、新設法人の多くは持分なしで設立されている一方、既存法人からの移行はまだ限定的であることがうかがえます。このように数字を追うと、実に15年以上かって持分なし医療法人はやっと全体の約4割といったところです。なお持分あり医療法人の減少には、解散した法人も含みますので、持分なし医療法人の増加のうち新設法人が多くを占め、持分ありから持分なしへ移行した医療法人は少ないことが予想されます。
*出典:厚生労働省統計「種類別医療法人の年次推移」
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001505575.pdf
持分あり医療法人は本当に有利? 財産権がもたらすメリットと誤解
持分あり医療法人は、出資持分(財産権)が認められている分、持分なし医療法人に比べて有利だと言われることがあります。医療法人は非営利ですから、黒字により生じた利益を出資者に配当することができません。しかし利益は法人内部に蓄積されていくため、利益剰余金が膨らみ、出資持分の評価額が高くなるケースが多く見られます。
このため、持分あり医療法人は「財産的価値を持つ法人」として、経営権を譲渡する際に創業者利益を確保しやすいという側面があります。実際、第三者に法人を譲渡する際には、当初の拠出額に加えて、利益剰余金の一部も出資持分の評価額に反映され、結果的に「財産を伴う譲渡」が成立します。こうした仕組みが、「持分あり医療法人の方が有利」と言われる理由です。一方で、持分なし医療法人では当初の拠出額しか受け取ることができず、利益剰余金については国などに寄付しなければなりません。創業者利益を受け取ることができないように見えますので、持分なし医療法人について不公平感を覚える医師が多いことも納得できます。
持分なし医療法人は“相続税対策”になることも
一見すると、持分なし医療法人は創業者利益を受け取れないため「損」に見えるかもしれません。しかし、実際には持分あり医療法人よりも税制面で有利になるケースもあります。蓄積された利益剰余金は、退職金として受け取ることが可能です。出資持分の払戻として受け取るか、退職金として受け取るかの違いだけで、実質的には同様の利益を確保することができます。つまり、持分なし医療法人であっても、創業者の努力に見合う対価を退職金という形で受け取ることができるのです。
さらに親子間承継を想定する場合には、むしろ節税効果が期待できることもあります。利益剰余金を退職金として引き出さず、法人内部に留保したまま次世代に経営を引き継ぐことで、相続税の評価額を抑えることが可能です。このように、持分なし医療法人は「財産権がない=損」という単純な構図ではなく、設計次第で節税と継承を両立できる柔軟な法人形態といえるでしょう。
M&Aの観点で見る資本構造の違い
医療法人を譲り受ける側が医師個人の場合、法人の利益剰余金は将来退職金として受け取ることができるため、「持分あり」「持分なし」の違いが大きく影響するケースはあまり多くありません。一方で、株式会社などの法人が買収して医療経営を行う場合は、事情が変わります。医療法人は非営利法人であるため、利益を株主に分配する「配当」や「出資金の払い戻し」ができません。また、株式会社の経営者が医療法人から退職金を受け取ることもできません。つまり、株式会社が出資して医療法人を運営しても、その資本を回収する手段がほとんどないのです。出資額に応じた利益を取り戻すには、医療法人を解散して清算するしか方法がないのが現実です。
その点、持分あり医療法人であれば、内部に蓄積された利益剰余金を出資持分の評価額に反映させることができます。出資持分を第三者に譲渡することで、資本に見合ったリターンを得ることが可能になります。したがって医師が自ら引き継いで経営を続ける場合には、持分なし医療法人でも何ら支障はありません。しかし、将来的にM&Aや第三者への譲渡も視野に入れる場合には、出資持分のある法人形態のほうが柔軟な対応がしやすく、買い手が見つかりやすい傾向にあります。
持分なし医療法人の特徴と、M&Aで見られる実務的メリット
ここまで見てきたように、「持分あり」と「持分なし」にはそれぞれ異なるメリットがあります。では、そもそも持分なし医療法人とはどのような仕組みで、なぜいま注目されているのでしょうか。その基本的な特徴と、実際のM&Aで評価されるポイントを見ていきましょう。
メリット:M&Aで評価される、透明性と安定性
持分なし医療法人は、出資者個人が法人資産を所有せず、残余財産も分配されない構造です。このため、経営の属人化を防ぎ、譲渡や承継の際に資産評価のトラブルが起こりにくいという特徴があります。特に第三者継承(医療法人M&A)の場面では、「誰のものか」が明確であることがスムーズな交渉につながり、買手様側からもガバナンスが整った法人として評価されやすくなります。また、出資持分の精算が不要であるため、持分あり法人に比べてスキーム設計がシンプルです。解散・清算リスクが低く、譲渡完了後のトラブルも抑えられる点は、M&Aを実務で進めるうえで大きなメリットといえるでしょう。
メリット:税務・会計面での扱いやすさ
持分なし医療法人では、法人内部に蓄積された利益が出資者個人の資産と見なされないため、相続税評価額が低く抑えられる傾向があります。また、医療法人の資産や利益は法人に帰属するため、経営者交代後の会計処理が明確で、金融機関からの信頼性も高くなります。その結果、譲渡後の事業継続がしやすく、地域医療を継続させるM&A案件としても評価が高い傾向にあります。
持分なし医療法人のM&Aにおける留意点
持分なし医療法人は、制度上の透明性や手続きのシンプルさから、M&Aの現場でも評価されやすい法人形態です。しかし、実際に譲渡を検討する際には、いくつか注意すべきポイントがあります。まず、出資者個人の対価をどのように整理するかという点です。持分なし医療法人では出資者個人に財産権がなく、法人譲渡の際に「経営者個人が得られる金銭的リターン」が曖昧になりがちです。そのため、譲渡契約の設計段階で、役員退職金や顧問料など、正当な報酬をどのように位置づけるかを事前に検討しておく必要があります。
また、内部留保の扱いも重要です。蓄積された利益剰余金は法人内部に留まるため、どの程度を退職金・人件費・設備投資に充てるかといった経営判断が、今後の安定性を左右します。
この方針を明確にしておくことで、買い手からの信頼も得やすくなります。さらに譲渡スキームの違いにも注意が必要で、持分なし医療法人では法人自体を譲渡することはできず、実際のM&Aでは「事業譲渡」という形を取るケースが中心となります。譲渡対象は、医療機器やスタッフ、診療ノウハウ、患者さんの基盤といった「医院の実体」です。法的・税務的な整理が必要になるため、早い段階から専門家に相談することが望ましいでしょう。
医院継承・クリニックM&Aに関する無料相談実施中
いかがでしたでしょうか。「持分あり」「持分なし」どちらの医療法人が有利かは、一概に結論づけられるものではありません。相続や税務を重視するなら持分なし、譲渡やM&Aでの柔軟さを求めるなら持分ありといったように、最適な選択は先生がどのように医院を次世代へ引き継ぎたいかによって異なります。
大切なのは、制度の仕組みを正しく理解し、将来の方向性に沿った準備を早めに始めることです。医院の資産構造や法人形態、譲渡スキームの違いによって、どのタイミングでどんな準備をすべきかが、大きく変わってきます。メディカルプラスでは、医院継承や医療法人M&Aをお考えの先生に向けて、随時無料相談を実施しています。ご要望に応じて、案件ごとの事業収支シミュレーションの作成など、具体的な検討もサポートいたします。医院継承(承継)、クリニックの売却・買収、医療法人M&Aをご検討中の方は、こちらより【お問合せ】お気軽にお問い合わせください。
クリニック譲渡案件と、譲受希望者条件が閲覧可能になります。また最新の譲渡案件・継承開業に関する情報をいち早くお届けするほか、資料のダウンロードも無制限で可能になります。情報収集の効率化にお役立てください。
この記事の著者

豊島 太郎(とよしま たろう)
株式会社メディカルプラス コンサルティング営業本部 医院継承事業部 リーダー
豊富な業界経験に加え二級建築士の資格を持ち、クリニックの内装やインテリア関連の知識にも明るい多才なアドバイザー。建設不動産関連業務を約7年経験、その中で人それぞれの人生とその大切さについて深く考える出来事を多く経験。メディカルプラス参加後は5年間で約40件以上の継承に立ち会い、医師の人生のターニングポイントに立ち会うやりがいを原動力にサポートを行う。穏やかな物腰と優れた傾聴力に社内外から定評あり。
人気記事
- 2025年08月15日
 譲渡 譲受
譲渡 譲受MS法人とは?医療法人との違いと取引時の注意点
こんにちは。医院継承・クリニックM&A支援のメディカルプラスです。院長先生や開業をご検討中の先生方とお話しすると、よく出てくるのが次のようなご質問です。 - 2025年08月08日
 譲受
譲受一般社団法人のクリニック開設方法 ~注意点と医療法人との違い~
こんにちは。医院継承・クリニックM&A支援のメディカルプラスです。今回は、弊社で継承支援の際に先生方と話題になることが多い「一般社団法人によるクリニック開設方法」について解説いたします。近年、「一般社団法人」という法人形態でクリニックを開設するケースが注目されており、2023年以降は一部都市部で実際の開設事例も見られ - 2024年10月04日
 譲渡 譲受
譲渡 譲受医院継承時のスタッフ雇用引継ぎについて
こんにちは。クリニック継承(承継)、クリニックM&A、医療法人M&Aを支援しているメディカルプラスです。本日はクリニック継承(承継)時の既存スタッフの雇用引継ぎについてお伝えします。クリニック継承時、既存スタッフの雇用を引き継ぐかどうかは、譲渡される先生、譲受される先生双方にとって非常に重要な課題です。スタッフの引き継ぎには、クリニック運営の安定を図るための多くのメリットがある一方、リスクや課題
最新記事
-
 譲渡
譲渡クリニック閉院(廃院)時の医療機器の処分方法について
こんにちは。医院継承・クリニックM&A仲介支援のメディカルプラスです。クリニックを閉院(廃院)する際には、さまざまな実務が発生しますが、その中でも「医療機器の扱い」は判断に迷われる先生が多い領域です。高額な設備であることに加え、廃棄や再販には法的な手続きや専門的な対応が必要になるため、早い段階で全体像を把握しておくことが大切です。本記事では、閉院時の医療機器 -
 譲渡 譲受
譲渡 譲受クリニック閉院(廃院)時に必要な手続きについて
こんにちは。医院継承・クリニックM&A仲介支援のメディカルプラスです。日頃より、閉院(廃院)と譲渡(継承)のどちらを選ぶべきか悩まれている院長先生から、さまざまなご相談をいただきます。その中でも特に多いのが、「閉院を選択する場合、どのような手続きが必要なのか」というお問い合わせです。過去記事では、廃院に伴うおもな費用やその背景にある負担について、また -
 譲渡 譲受
譲渡 譲受クリニック閉院(廃院)には1,000万円以上かかることも ~どんな費用が必要?~
こんにちは。医院継承・クリニックM&A仲介支援のメディカルプラスです。過去記事では、引退期を迎えた際にどのような選択肢があるのか、閉院(廃