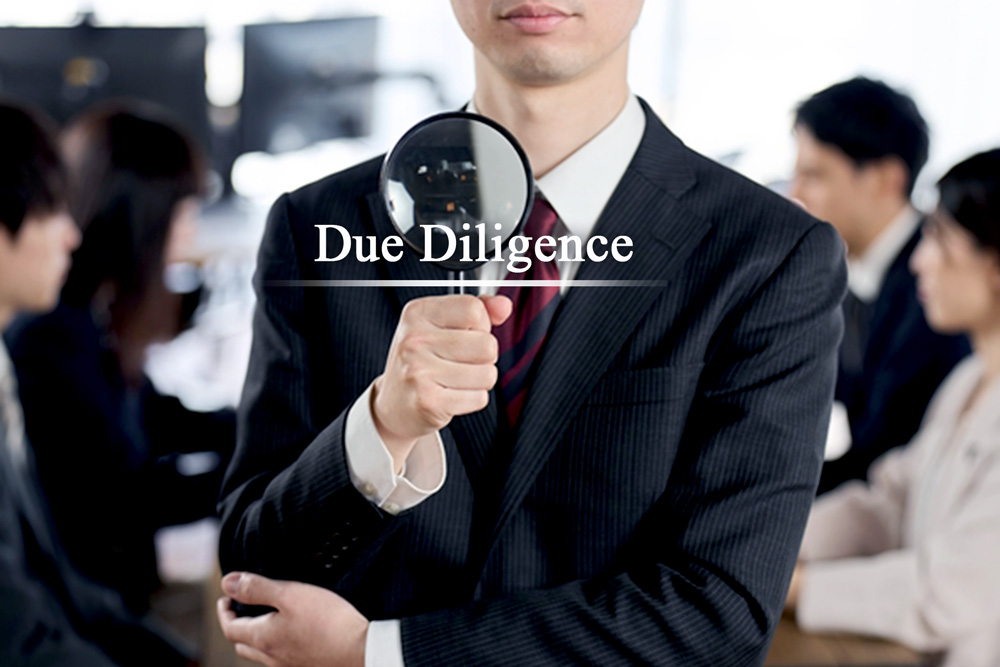一般社団法人のクリニック開設方法 ~注意点と医療法人との違い~

INDEX
こんにちは。医院継承・クリニックM&A支援のメディカルプラスです。今回は、弊社で継承支援の際に先生方と話題になることが多い「一般社団法人によるクリニック開設方法」について解説いたします。近年、「一般社団法人」という法人形態でクリニックを開設するケースが注目されており、2023年以降は一部都市部で実際の開設事例も見られるようになりました。とはいえ、その数はまだ多くありません。本記事では「一般社団法人とは何か」、「開設までの方法と注意点」、「医療法人との違い」について、2025年時点の情報を交えてお伝えしますのでご参考ください。
一般社団法人と医療機関運営の関係
医療法人以外の選択肢として、近年注目を集めているのが一般社団法人による医療機関運営です。一般社団法人は営利を目的としない法人形態で、一定の条件を満たせば病院や診療所などの開設主体となることが可能です。医療法人に比べ設立手続きや事業運営の自由度が高い一方で、医療分野で活動する場合には、非営利性の徹底や行政からの許可取得といった法的要件を確実にクリアしなければなりません。
近年では、病院・診療所の運営だけでなく、医療系の研究・学会運営、地域医療の連携組織などでも一般社団法人の活用が見られます。これにより、医療法人とは異なる形で地域医療や専門医療サービスに貢献できる可能性があります。ではそもそも「一般社団法人」とは何かについて、見ていきましょう。
一般社団法人とは?
一般社団法人は、平成20年12月の「公益法人制度改革」により誕生した、営利を目的としない法人格です。この改革では「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(一般法人法)など関連三法が施行され、「一般社団法人」と「一般財団法人」の2つの法人形態が設立可能になりました。
両者の大きな違いは、その成り立ちにあります。一般社団法人は人(社員)の集まりとして設立されるのに対し、一般財団法人は財産の集まりとして設立されるため、設立時に一定の財産(基金)を拠出する必要があります。また、「非営利」とは利益を出してはいけないという意味ではなく、事業活動で利益を上げても構いませんが、その利益を社員や出資者に配分することはできません。毎期ごとの配当は不可ですが、解散時には残余財産を分配できる点は、出資持分なし医療法人との大きな違いです。2025年現在、この制度の基本は変わっておらず、医療分野でも理解しておくべき法人形態のひとつです。
一般社団法人と一般財団法人は以下のような違いがあります。
| 一般社団法人 | 一般財団法人 | |
| 特徴 | 人の集まり | 財産の集まり |
| 目的 | 制限なし | |
| 社員資格 | 制限なし | |
| 社員又は設立数 | 2人以上 | 1人以上 |
| 役員 | 理事1名以上 | 評議員3人以上、理事3人名以上、監事1名以上 |
| 役員任期 | 理事2年以内、監事4年以内(※選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時まで。監事は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時まで。) | |
| 基金 | 制限なし | 300万円以上 |
| 配当 | 不可 | |
一般社団法人、一般財団法人の設立は以下の方法により行うことができます。見ていきましょう。
2-1. 一般社団法人設立までの流れ
一般社団法人設立までの流れは、次の①~➃で行われます。
➀. 定款を作成し、公証人の認証を受ける
➁. 設立時理事の選任を行う
➂. 設立時理事が設立手続きの調査を行う
➃. 設立時理事もしくは設立時代表理事が法定期限内に管轄の法務局へ設立登記申請を行う
2-2. 一般財団法人設立までの流れ
次に一般財団法人設立までの流れです。次の①~➄で行われます。
➀. 定款を作成し,公証人の認証を受ける。
➁. 設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。
➂. 定款の定めに従い,設立時評議員,設立時理事,設立時監事の選任を行う。
➃. 設立時理事及び設立時監事が設立手続の調査を行う。
➄. 設立時代表理事が法定期限内に管轄の法務局へ設立登記申請を行う
また一般社団法人のなかから公益性の認定を受けた法人は公益社団法人になることができ、公益社団法人になると税制上の優遇を受けることができます。一般社団法人及び一般財団法人の法人税制は以下の通りとなります。
| 一般社団法人・一般財団法人 | 公益社団法人 公益財団法人 | ||
| 非営利型法人以外の法人 | 非営利型法人 | ||
| 法人税の法人区分 | 普通法人 | 公益法人等 | |
| 課税所得範囲 | 全ての所得が課税対象 | 収益事業から生じた所得が課税対象 | |
※2025年現在も、一般社団法人・一般財団法人の設立手続きや公益法人制度に大きな変更はなく、上記の流れで設立が可能です。自治体によって細部の運用や必要書類が異なる場合があるため、事前確認を推奨します。
一般社団法人でクリニックを開設することはできるのか?
ここまでは一般社団法人の概要についてお伝えしてきました。ここからは、そもそも一般社団法人でクリニックを開設できるのかというテーマに焦点をあて、法的な位置づけや条件について解説していきます。まずは、病院や診療所など医療機関には非営利性が求められているという基本的な前提から確認しましょう。
医療機関の非営利性については、医療法に2つの重要な規定があります。1つ目は医療法第七条6項で、「営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては開設許可を与えないことができる。」と定められています。2つ目は医療法第五四条で、「医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。」と規定されています。つまり、これらの規定により日本では営利目的で医療機関を開設することはできない、というのが大前提になります。
次に、病院や診療所の開設主体について見ていきましょう。現在の医療法では、特定の法人を開設者から排除する規定はなく、前述の通り「営利を目的とした開設」を規制するにとどまっています。こうした中、平成20年12月の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」施行に先立ち、厚生労働省は平成19年3月30日に「医療法人以外の法人による医療機関の開設者の非営利性の確認について」(医政総発第0330002号)という通知を発出しました。
この通知では、次のように記されています。
「近年、特定非営利活動法人や、今般の公益法人制度改革による一般社団法人・一般財団法人など、従来の法人と比べて簡易な手続きで法人を設立できる仕組みが整備されてきていることから、平成五年通知に定める『医療機関の開設者に関する確認事項』については、従来以上に慎重に確認の上、対処されたい。」
「開設許可の審査に当たり、医療法人以外の法人が開設した医療機関について、解散した場合の残余財産が帰属すべき者に関する規定が、あらかじめ定款、寄附行為等で定められており、かつ、その者は、出資者又はこれに準ずる者以外の者であること。」
つまりこの通知は、一般社団法人による病院や診療所の開設を禁止するものではありません。ただし、開設主体となる一般社団法人については、非営利性を厳正に確認・審査したうえで許可を出すよう求めているのです。
それでは、一般社団法人で病院や診療所を開設する場合、どのようにすれば非営利性が認められるのでしょうか。その判断基準となるのが、法人税法(法人税法第2条9の2イ、法人税法施行令3条1項)で定められた「非営利性が徹底された法人」の要件です。この要件を満たすことで、当該法人は非営利性があると認められ、医療機関の開設主体となることが可能になります。
■「非営利性が徹底された法人」の要件
| 要件 | |
| 非営利性が徹底された法人 | ①剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。 |
| ②解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。 | |
| ③上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該 当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含み ます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。 | |
| ④各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の 1 以下であること。 |
*出典:
法人税法 第2条第9号の2イ(e-Gov法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000034
法人税法施行令 第3条第1項(e-Gov法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000097/
(最終確認:2025年8月8日)
一般社団法人と医療法人社団の違いについて
ここまで一般社団法人による病院・診療所の開設についてお伝えしてきました。では次に、一般社団法人と医療法人社団の違いについて見ていきましょう。まず、医療法人社団を設立する際には、都道府県の認可を受ける必要があります。認可までには事前協議からおおよそ半年ほどかかり、申請はいつでもできるわけではありません。行政が定めた年2回のスケジュールに合わせて申請を行う必要があります。一方、一般社団法人は前述のとおり、定款を作成して役員を選任し、法務局へ登記申請を行えば設立が可能です。手続きの複雑さや所要期間の面で、医療法人社団よりもはるかに容易だといえます。
また、医療法人は医療法に基づく年1回の行政への事業報告義務に加え、医療や介護以外の事業は行えません。さらに、分院の開設や施設名称の変更、所在地の移転などを行う際には、その都度、行政の定款変更認可を受けなければなりません。これに対し、一般社団法人にはこうした規制はなく、事業運営の自由度が高いのが特徴です。一般社団法人と医療法人社団の違いを以下の表にまとめましたので、ご参考ください。
■一般社団法人と医療法人社団の比較
| 一般社団法人 | 医療法人社団 | |
| 設立 | 登記のみ | 都道府県の認可及び登記 |
| 病院、診療所開設 | 保健所の許可 | 保健所の許可 |
| 申請時期 | 制限なし(随時可能) | 年2回 |
| 設立までの時間 | 要件なし | 概ね半年程度 |
| 拠出金 | 要件なし | 都道府県ごとに制限あり |
| 理事長要件 | 要件なし | 医師又は歯科医師 |
| 業務制限 | 制限なし | 制限有り (医療、介護など付帯業務のみ可能) |
| 社員 | 1人以上 | 3人以上 |
| 役員 | 1人 | 理事3人、監事1人以上 |
| 利益剰余金の分配 | 不可 | 不可 |
こうして比較してみると、一般社団法人のほうが医療法人社団よりも自由度が高いことがよく分かるのではないでしょうか。特に、クリニックの事業承継という観点から見れば、医療法人に比べてメリットが際立ちます。たとえば、医療法人では事業承継に伴い分院の廃止や施設名称の変更などの手続きが必要になりますが、一般社団法人ではこうした行政手続きが不要です。これにより、手続きの簡略化や迅速な承継が可能になります。
さらに、定款変更に伴う行政書士への報酬が不要、もしくは大幅に抑えられるため、コスト削減にも直結します。結果として、事業承継をスムーズかつ効率的に進められる点は、一般社団法人ならではの大きな強みと言えるでしょう。
一般社団法人によるクリニック開設の注意点
ここまで、一般社団法人によるクリニック開設や医療法人社団との違いについて解説してきました。2025年時点での注意点をお伝えすると、まず一般社団法人による病院・診療所の開設事例は全国的にはまだ少数で、現在も多くは個人医師もしくは医療法人社団による開設が主流です。ただし2023年時点で一般社団法人による医療機関開設の事例は増えてきており、病院が82件(+6件)、医科診療所が780件(+396件)、歯科診療所が151件(+42件)という統計が厚生労働省の調査で明らかになっています(全国47都道府県中45都府県の回答に基づく)
*厚生労働省調査結果PDF
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/562280.pdf
とはいえ、全体の数からするとまだ多くはなく、地域によって許可の進捗にはかなり差があるのが現実です。現行の医療法では一般社団法人による開設を制限する規定はありませんが、病院・診療所を開設するには保健所の許可が必要です。前例が少ない地域では、許可までに時間がかかったり、認められない場合もあります。行政は新しい前例をつくることに慎重なため、こうしたリスクを避けるためには、事前に管轄の保健所と協議を行うか、一般社団法人による医療機関開設の実績を持つ行政書士などの専門家に相談することをお勧めいたします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
一般社団法人は、条件を満たすことで病院や診療所などの医療機関を開設することが可能であり、設立手続きの容易さや事業運営の自由度といったメリットがあります。一方で、全国的にはまだ事例が少なく、地域によって許可取得の難易度が大きく異なるのが現実です。2023年の厚生労働省調査では、病院82件、医科診療所780件、歯科診療所151件と増加傾向にあるものの、事前の行政との協議や専門家の関与が成功のためには必要とお考えいただければと思います。
医院継承・開業に関する無料相談実施中
弊社は2016年の創業以来、地域医療の継続と発展への貢献をモットーに掲げ、一貫してクリニックに特化した医院継承支援を行っております。医院の譲渡・譲受や新規開業に関する無料相談を随時実施しており、行政書士をはじめとした専門家のネットワークも豊富にございますので、クリニックM&Aは継承開業、分院展開についてご関心のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
クリニック譲渡案件と、譲受希望者条件が閲覧可能になります。また最新の譲渡案件・継承開業に関する情報をいち早くお届けするほか、資料ダウンロードが可能になります。情報収集の効率化にお役立ください。
人気記事
- 2025年08月15日
 譲渡 譲受
譲渡 譲受MS法人とは?医療法人との違いと取引時の注意点
こんにちは。医院継承・クリニックM&A支援のメディカルプラスです。院長先生や開業をご検討中の先生方とお話しすると、よく出てくるのが次のようなご質問です。 - 2025年08月08日
 譲受
譲受一般社団法人のクリニック開設方法 ~注意点と医療法人との違い~
こんにちは。医院継承・クリニックM&A支援のメディカルプラスです。今回は、弊社で継承支援の際に先生方と話題になることが多い「一般社団法人によるクリニック開設方法」について解説いたします。近年、「一般社団法人」という法人形態でクリニックを開設するケースが注目されており、2023年以降は一部都市部で実際の開設事例も見られ - 2024年10月04日
 譲渡 譲受
譲渡 譲受医院継承時のスタッフ雇用引継ぎについて
こんにちは。クリニック継承(承継)、クリニックM&A、医療法人M&Aを支援しているメディカルプラスです。本日はクリニック継承(承継)時の既存スタッフの雇用引継ぎについてお伝えします。クリニック継承時、既存スタッフの雇用を引き継ぐかどうかは、譲渡される先生、譲受される先生双方にとって非常に重要な課題です。スタッフの引き継ぎには、クリニック運営の安定を図るための多くのメリットがある一方、リスクや課題
最新記事
-
 譲渡 譲受
譲渡 譲受クリニック閉院(廃院)時に必要な手続きについて
こんにちは。医院継承・クリニックM&A仲介支援のメディカルプラスです。日頃より、閉院(廃院)と譲渡(継承)のどちらを選ぶべきか悩まれている院長先生から、さまざまなご相談をいただきます。その中でも特に多いのが、「閉院を選択する場合、どのような手続きが必要なのか」というお問い合わせです。過去記事では、廃院に伴うおもな費用やその背景にある負担について、また -
 譲渡 譲受
譲渡 譲受クリニック閉院(廃院)には1,000万円以上かかることも ~どんな費用が必要?~
こんにちは。医院継承・クリニックM&A仲介支援のメディカルプラスです。過去記事では、引退期を迎えた際にどのような選択肢があるのか、閉院(廃 -
 譲渡 譲受
譲渡 譲受閉院(廃院)、それとも譲渡(継承)? ~クリニック引退時の判断ポイント~
こんにちは。医院継承・クリニックM&A仲介支援のメディカルプラスです。当社では、クリニックに特化した事業継承支援を専門領域とし、新規開業を検討されている先生から、長年の診療を終え「そろそろ区切りを…」と感じておられる院長先生まで、幅広いご相談を日々お受けしています。その中で多くの先生に共通しているのが、「引退を迎えるとき、閉院(廃院)と譲渡(継承)のどちらを選ぶべきか」というお悩みで